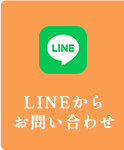お盆の季節の迎え火と送り火
先祖の霊をお迎えするのが迎え火、送るのが送り火です。
迎え火は先祖の霊が帰ってくるときの目印になり、送り火は私たちがしっかりと見送っているという証になります。
迎え火は家の門口や玄関で行う場合もあれば、お墓で行う地域もあるなど、その形態はさまざまです。
一般的には、家の門口や玄関で、素焼きのお皿の上でオガラを焚いて、先祖の霊を迎えます。
お墓で行う場合は、お墓参りをしたあと、お迎え用の提灯に明かりを灯して、その明かりと共に先祖の霊を家まで導いて帰ります。
ちなみに、故人がはじめてこの世に戻ってくることを「初盆」といい、迷わないで戻って来られるように、家の外に高い柱を設けて提灯をつける「高提灯」で迎え入れます。
迎え火は7月13日(8月13日)、送り火は7月16日(8月16日)に行うのが一般的です。
13日の夕方、家の門口や玄関で、素焼きの焙烙にオガラを折って積み重ね、
火をつけて燃やし、迎え火として先祖の霊を迎えます。
オガラを燃やしたその煙に乗って、先祖の霊が家に帰ってくるともいわれています。
16日の夕方には再び同じ場所で、焙烙にオガラを折って積み重ね、火をつけて燃やし、
送り火として先祖の霊を送り出します。
最近では写真のようなキャンドルも販売しています。
割り箸などを用いて、きゅうりは「馬」、なすは「牛」に見立てて作るお供物を「精霊馬(しょうりょううま)」といいます。
先祖の霊は、この「精霊馬」に乗ってこの世に戻り、あの世に帰っていくと考えられていて、早く走れる「馬」が迎えに行き、ゆったり歩く「牛」が送っていきます。
今では都市部を中心に飾りつけは簡素化され、ホームセンターやスーパーなどで販売されている飾りつけセットを使う家庭も多いようですが、江戸時代においても、都市部の人々は、地方からやって来る農家による「盆市」や「ほおずき市」などで飾りつけ用具を購入していたようです。
お盆は日本ならではの行事
今や仏教行事に取り入れられた形で行なわれている「お盆」ですが、実は、仏教が起源の行事ではないのです。お供物を例にすると、仏教では殺生を忌み嫌うため、動物や魚の肉は取り入れませんが、神道では動物の血肉を嫌うことはなく神饌(しんせん=神様へのお供物)にも獣肉や魚を用います。「お盆」はというと、夏野菜のほかに生魚をお供えします。このようなことから、仏教の行事ではなかったことが分かります。「お盆」とは、江戸時代以前にあった「神仏習合」の思想のもとで始まった日本独自の行事だといえます。
16日のこの日に、お盆の間の一緒にすごした祖先の霊を送り出すことを「精霊送り」とも言われています。この時に「送り火」を焚くことも広くおこなわれています。
ちなみに京都の「大文字焼き」も送り火のひとつです。
有限会社松川仏壇
〒910-0067
福井県福井市新田塚1-87−13
TEL0776−27−5538
オフィシャルページ https://matsukawabutsudan.jp/